4月末の社中いけばな展、続く様々なイベントやお仕事で、このブログはおろかXやインスタも更新が止まったままになっている。
季節はすっかり夏で、連日の暑さの中での作品制作は、何かの拷問ではないかとさえ思ってしまう。
今日の夕方、サウナ状態の現場から帰宅し、ざっと汗を流した後にテレビをつけたら、古畑任三郎の再放送をやっていた。「しばしのお別れ」の回だ。
大好きな古畑任三郎、しかもこの回は私にとってとても印象深い。
華道家・二葉鳳翆(山口智子)は、家元・二葉鳳水(長内美那子)の元から独立してフラワーアレンジメント教室を経営していたが、鳳水から度々営業妨害を受けていた。鳳翆は発表会に鳳水を招待して密かに楽屋に呼ぶとネックレスを贈り、睡眠薬入りのお茶を飲ませ、発表会中に抜け出し客席で眠っている鳳水に毒物を注射、心臓発作に見せかけて殺害した。今泉の発表を見に来ていた古畑は病死に疑問を抱くが、鳳水は勝手に席を移動しており、犯人にその位置を知る術はなかった。
古畑任三郎事件ファイルより引用
この回の初回放送は1996年3月だから、私がいけばなを始めて間もないころである。当時はいけばながどうというより、古畑任三郎が、そして三谷幸喜が好きで見ていた。
このブログで何度も取り上げているイベントの話で恐縮なのだが、2010年に「座・高円寺」で上演した「Yuming Tribute Piano Concert」で共演した、ピアニスト・笛木健治氏も同じく三谷ファンであり、このイベントの構成や演出を考える上で一番初めに話題となったのが、この「しばしのお別れ」である。
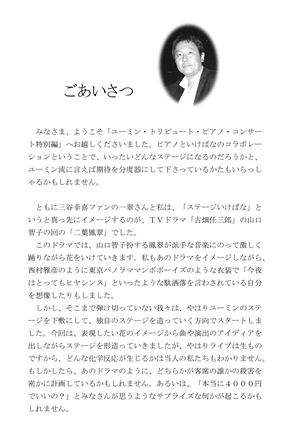
当時のパンフレットに掲載されていた笛木氏の文章にも、この件が触れられている。少し抜粋。
【前略】
ともに三谷幸喜ファンの一翠さんと私は、「ステージいけばな」というと真っ先にイメージするのが、TVドラマ「古畑任三郎」の山口智子の回の「二葉鳳翠」でした。
このドラマでは、山口智子扮する鳳翠が派手な音楽にのって激しく踊りながら花をいけていきます。私もあのドラマをイメージしながら、西村雅彦のように東京パノラママンボボーイズのような衣装で「今夜はとってもヒヤシンス」といったような駄洒落を言わされている自分を想像したりもしました。
【中略】
もしかしたら、あのドラマのように、どちらかが客席の誰かの殺害を密かに計画しているかもしれません。
【後略】

文中に出てくる西村雅彦とは、古畑任三郎の部下、今泉慎太郎のことである。
それにしても「東京パノラママンボボーイズ」あたりがスラスラ出てくるあたり、笛木氏の文才とユーモアセンスは素晴らしい。
偶然の一致
さて、今回改めて「しばしのお別れ」を観て、今の私と状況が似ていることに驚いている。
あれから私は流派を離れて活動している。流派を離れるとき、私のお弟子も一緒に退会した。ステージで花をいけることもある。
大きく違うのは、今でも元所属流派とは良好な関係であること、私は誰の殺害も計画していないこと(ここ重要)、そして踊りながら花をいけていないことだ。
いや、今後もしかしたら踊りながらいけることはあるかもしれない。あちらがフラメンコやマンボなら、私は日本舞踊だ。


「今夜はとってもヒヤシンス 明日は雪がフリージア」をやろうと思ったら、地唄「雪」がいいかもしれない。相変わらずアホくさい妄想である。
それにしても、花をいけるだけでなく、そこにもう一つのパフォーマンスを組み合わせるのは、面白い試みだと思う。
そんな話を高円寺の打合せ時に話していたもんだから、本番後に「いきなり歌いだすんじゃないかと思ってヒヤヒヤした」と笛木氏から言われた。
あの当時はそんな大それたことできるはずもないと思っていたが、今の自分だったら歌っていたかもしれない。年月って怖い。
その後も、私の歌好きをご存じの方からも「いっそ歌いながら花をいけたらどうだ」とご提案いただいたことが何度もある。
蛇足だが、エンジン全開の(要は調子よく酔っ払った)私は、ライオンキングの「ハクナマタタ」だの、レ・ミゼラブル「民衆の歌」だのと、ミュージカルナンバーをマイクなしで歌い、同席者から「声量オバケ」やら「4次元ミュージカル俳優」などと評される。
きっと本心は「やかましい」「時空を超えた頓珍漢」と言いたいのだろうから、ちっとも褒められてはいない。一言でいえば「カラオケで同席したら迷惑な人」なわけで、なんか…ごめん。
棒状のオブジェ
話を元に戻そう。
もう一つ、改めてこのドラマを観ていて驚いたのは、舞台セットである。2010年上演時、雨をイメージした青い棒(これを「雨のオブジェ」と呼んでいた)に花をいけ、6月の雨の風景を、雨にまつわる曲の演奏に合わせ表現した。


似てるっちゃ似てる
その雨のオブジェと似たようなものが、古畑任三郎のステージ上にもあるではないか!
ただただ偶然の一致なのだが、初回放送から30年近く経ってこんなことに気づくなんて、私もまだまだ古畑ファンなんぞとは到底言えないなと、30年近く経っても痛感している。
